「時間をかけて作り込んだ資料なのに、『結局、何が言いたいの?』と一言で終わらされた…」 「内容には自信があるのに、なぜか相手にうまく伝わらない…」
資料作成において、そんな悔しい経験はありませんか?
実は、多くの「伝わらない資料」の原因は、見た目のデザインやグラフの精緻さではなく、その土台となる「文章の書き方」にあります。どんなに優れた分析や画期的なアイデアも、それを伝える文章が分かりにくければ、価値は半減してしまうのです。
この記事では、小手先のデザインテクニックではなく、ライティングの観点に絞って、読み手の心を動かし「一発OK」を引き出すための具体的な文章術を解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは単なる「資料を作る人」から、「文章で人を動かし、仕事を生み出す人」へと変わっているはずです。
なぜあなたの資料は伝わらないのか?
具体的なライティングテクニックを学ぶ前に、まず最も重要な「考え方(マインドセット)」についてお話しします。なぜなら、この土台がなければ、どんなに優れたテクニックも効果を最大限に発揮できないからです。
「自己満足な資料」と「伝わる資料」の決定的な違い
多くの人が時間と労力をかけているにもかかわらず、無意識のうちに「自己満足な資料」を作ってしまっています。これは、資料の主役が「書き手」になってしまっている状態です。「伝わる資料」を作るには、主役を「読み手」に交代させなければなりません。
| 自己満足な資料(書き手が主役) | 伝わる資料(読み手が主役) | |
| 目的 | 自分の知識や努力をすべて盛り込む | 読み手の疑問に答え、行動を促す |
| 視点 | 「私はこう考えた」「こんなに調べた」 | 「あなたはこうなれる」「知りたいのはこの点ですよね?」 |
| 結果 | 「情報量は多いが、要点不明」 「結局、何が言いたいの?」 | 「次に何をすべきか明確になった」「なるほど、よく理解できた」 |
あなたが書くべきは、自分の頑張りを物語る分厚い記録書ではなく、読み手の貴重な時間を奪わずにゴールまで導く、洗練された地図なのです。
すべては「読み手ファースト」の精神から始まる
では、どうすれば主役を「読み手」にできるのか。その答えが、この教科書の最も重要なキーワードである「読み手ファースト」です。
これは、資料を書き始める前、そして書いている最中に、常に以下の3つを自問自答し続ける姿勢を指します。
- この資料の読み手は「誰」か? (Who?)
- 読み手の役職や役割は何ですか?(社長向け?現場の担当者向け?)
- 前提となる知識をどれくらい持っていますか?
- 何に関心があり、何を懸念していますか?
- (例:社長向けなら詳細なデータより「結論とインパクト」、担当者向けなら「具体的な手順や背景」が重要)
- 読み手は「何」を知りたいか? (What?)
- あなたが伝えたいことではなく、相手が意思決定のために知るべき情報は何ですか?
- この資料を読んで、相手はどんな疑問を抱くでしょうか?その疑問に先回りして答えられていますか?
- 読み手に「どうなってほしい」か? (How?)
- この資料を読み終えた後、相手にどんな気持ちになり、どんな行動を起こしてほしいですか?
- (例:リスクを理解し、計画を承認してほしい。新方針に納得し、協力を約束してほしい。)
資料作成は、相手の時間をいただいて行うプレゼンテーションと同じです。文章のひとことひとことに「おもてなしの心」を宿らせる。それが「読み手ファースト」の第一歩であり、伝わる資料を作るための唯一の土台となります。
これだけ押さえればOK!伝わる文章 3つの基本原則
マインドセットが整ったら、次はいよいよ具体的なライティングテクニックです。この章で紹介する3つの原則を実践するだけで、あなたの資料は劇的に分かりやすくなり、説得力が増します。
原則1:ゴールから逆算する -「で、どうしてほしいの?」に1秒で答える
第1章で触れた「読み手にどうなってほしいか」を、文章を書く上での「コンパス」として使いこなすテクニックです。優れた資料は、常に明確なゴールから逆算して作られています。
これを実践する最も簡単で効果的な方法は、資料を作り始める前に、PCのメモ帳やノートの1行目に、その資料のゴールを書き出すことです。
【ゴールの設定例】
この資料のゴール:〇〇部長に、新しいマーケティング施策A案の予算100万円を承認してもらうこの資料のゴール:△△チームに、プロジェクトの進捗遅延を正しく理解してもらい、B案への協力に合意してもらう
この「ゴール宣言」を常に視界に入れておくことで、書くべき内容がブレなくなります。「この情報は、ゴール達成に必要か?」と自問自答することで、不要な情報を大胆に削ぎ落とすことができるのです。
原則2:とにかく短く、具体的に – 読み手の「脳のメモリ」を消費させない
読み手は、あなたが思うよりずっと疲れています。長くて分かりにくい文章は、読み手の「脳のメモリ」を無駄に消費させ、内容を理解する前に集中力を奪ってしまいます。
以下のテクニックを使い、相手を疲れさせない「省エネ」な文章を心がけましょう。
- ①「一文一義」を徹底する 一つの文に込めるメッセージは一つだけ。目安は60文字以内です。文章が長くなったら、接続詞や句読点を使って2つに分けましょう。
- ②「箇条書き」を積極的に使う 3つ以上の項目を「〇〇や△△、□□など」と文章で並べるのはNGです。箇条書きを使えば、情報が視覚的に整理され、一瞬で理解できます。
- ③ 冗長な「お決まりフレーズ」を削る ビジネス文書で使いがちな、丁寧すぎて逆に分かりにくい表現は、思い切って削ぎ落としましょう。
| 冗長な表現(Before) | 簡潔な表現(After) |
| 〜することができます | 〜できます |
| 〜ということが分かりました | 〜が分かりました |
| 〜に関してですが | 〜は |
| 確認させていただきたく存じます | ご確認ください |
- ④ 抽象的な言葉を「数字」や「固有名詞」に置き換える
- 「頑張ります」「早急に」といった曖昧な言葉は、認識のズレを生む原因です。誰が読んでも同じ解釈ができる、具体的な言葉に変換しましょう。
- NG例:
コミュニケーションを密にして、プロジェクトを成功させます。 - OK例:
**A社の田中様**と**週1回30分の定例会**を実施し、プロジェクトの課題を解決します。
- NG例:
原則3:話の地図を見せる – 読み手を絶対に迷子にさせない
どんなに一文が分かりやすくても、話の順番がめちゃくちゃでは、読み手は話の途中で迷子になってしまいます。特に忙しい役職者ほど、まず「話の全体像」と「結論」を知りたがります。
そこでおすすめなのが、最強の論理構成フレームワーク「PREP(プレップ)法」です。
- P (Point):結論
私の提案は「営業プロセスのオンライン化」です。 - R (Reason):理由
なぜなら、訪問営業の非効率性が、売上停滞の主な原因となっているからです。 - E (Example):具体例・データ
例えば、営業担当者の移動時間は月平均20時間に達しており、これは人件費に換算すると年間〇〇万円の損失です。 - P (Point):結論(再)
したがって、営業プロセスをオンライン化し、移動時間を顧客との対話時間に充てることを提案します。
長い資料の冒頭で「本日は〇〇について、3つの観点からご説明します」とアジェンダを示したり、各スライドのタイトルを「〇〇の現状【結論:△△が課題】」のように結論が分かる形にしたりするのも、読み手を迷子にさせないための有効なテクニックです。
【シーン別】今すぐ使えるライティングフレーズ集
ここまで学んだ原則は、あらゆるビジネス資料に応用できます。この章では、特に利用頻度の高い「企画書・提案書」と「報告書・議事録」の2つのシーンに分け、そのまま使える便利なフレーズや構成の型をご紹介します。
1. 企画書・提案書で「説得力」を増すフレーズ
企画書や提案書のゴールは、読み手を説得し「承認」や「合意」といったアクションを引き出すことです。そのためには、論理的で、かつ相手のメリットが明確に伝わる文章が求められます。
■ 冒頭で相手を惹きつける「問題提起」の型
単に「〇〇を提案します」と始めるのではなく、相手が「確かに、それは問題だ」と共感するような書き出しをすることで、提案の価値が一気に高まります。
- 「〇〇という状況が続いていますが、このままでは△△というリスクがあります。」
- (例:「新規顧客の獲得数が3ヶ月連続で目標未達ですが、このままでは下半期の売上目標達成が困難になります。」)
- 「皆様も、〇〇という課題を感じていらっしゃるのではないでしょうか?」
- (例:「皆様も、日々の業務報告書の作成に時間がかかりすぎている、という課題を感じていらっしゃるのではないでしょうか?」)
■ 提案の価値を伝える「Before→After」の型
あなたの提案が承認されると、読み手の未来がどう変わるのかを具体的に示します。
- 「現状(Before)では〇〇という課題がありますが、本施策の実行により、△△(After)という状態を実現します。」
- (例:「現状では手作業で月20時間かかっている集計業務が、本ツールの導入により、月1時間に短縮され、より分析的な業務に集中できる状態を実現します。」)
■ 反論を先回りして潰す「懸念点と対策」の型
提案に対して想定される懸念点やリスクを正直に開示し、その対策をセットで示すことで、誠実さと信頼性が増します。
- 「〇〇という懸念点が考えられますが、これに対しては△△という対策を講じます。」
- (例:「導入初期には操作に慣れない社員からの問い合わせ増加が懸念されますが、これに対しては2週間のサポート窓口設置と、動画マニュアルの整備という対策を講じます。」)
2. 報告書・議事録で「分かりやすさ」を高めるフレーズ
報告書や議事録のゴールは、事実や決定事項を「正確」かつ「簡潔」に伝え、関係者間の認識を揃えることです。個人的な感想や冗長な表現は徹底的に排除します。
■ 冒頭で全体像を示す「サマリー」の型
忙しい読み手のために、文書の冒頭で「要するにどういうことか」を3行程度でまとめます。
- 「本報告書の要点:〇〇について、現状は△△であり、今後の対応として□□が必要です。」
- 「本会議の決定事項は以下の3点です。1. 〇〇の導入を決定、2. 担当は△△チーム、3. 次回報告は□月□日。」
■ 事実と意見を明確に分ける「客観表現」の型
報告書では、客観的な「事実」と、そこから言える自分の「考察」や「意見」を明確に区別することが信頼性の鍵となります。
- 事実の記述:
- 「〇〇のアンケート結果では、回答者の7割が『不満』と回答しました。」
- 考察・意見の記述:
- 「この結果から、〇〇のUIに根本的な問題があると考えられます。」
- 「したがって、早急なUI改修が必要だと判断します。」
■ 次のアクションを明確にする「ToDoリスト」の型
特に議事録では、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を明確に示さないと、会議が「話しただけ」で終わってしまいます。必ず最後にToDoリストを記載しましょう。
- 【決定事項と担当者(ToDo)】
・〇〇の市場調査(担当:佐藤さん、期限:8/31)・△△のワイヤーフレーム作成(担当:鈴木さん、期限:9/7)
【効率化の極意】AI活用で資料作成を高速化する
最後に、これまで解説してきたライティングの質を担保しつつ、作成スピードを劇的に向上させるためのAI活用術をご紹介します。AIを「優秀な副操縦士」として使いこなし、資料作成にかかる時間を半減させましょう。
1. 構成案(アウトライン)の壁打ち相手に
ゼロから資料の構成を考えるのは、最も時間のかかる作業の一つです。AIにたたき台を作ってもらい、思考の起点にしましょう。
指示の例: 「社内向けの新しい勤怠管理システム導入に関する企画書の構成案を、PREP法に沿って作成してください。」
→ AIは、「背景」「現状の課題」「提案内容」「導入効果」「費用対効果」「スケジュール」「懸念事項と対策」といった、網羅的な目次案を瞬時に提示してくれます。
2. 文章の要約とリライト(推敲・ブラッシュアップ)
自分で書いた文章は、客観的に見直すのが難しいものです。AIに第三者の視点から文章を磨いてもらいましょう。
- 要約: 長々と書いてしまった部分をAIに読み込ませ、「この文章を、冒頭に載せるための3行のサマリーにしてください」と指示すれば、簡潔な要約が手に入ります。
- リライト:「この文章を、もっと簡潔で分かりやすい表現に書き直してください」「専門用語を使わず、中学生でも理解できるように説明して」といった指示で、文章の質を向上させます。
3. 専門用語の「翻訳」アシスタントに
第1章で解説した「読み手ファースト」を実践する上で、AIは強力な武器になります。技術的な内容などを、専門知識のない相手に説明する際に活用しましょう。
指示の例: 「『API連携によるデータ同期の自動化』という技術的なメリットを、経理部長が理解できるように、コスト削減の観点から説明する文章を作成してください。」
→ AIは、「これまで手作業で3時間かかっていた請求データの入力作業が不要になり、人件費の削減と入力ミスの防止に直接繋がります」といった、相手の関心事に合わせた文章に「翻訳」してくれます。
4. メールや依頼文のドラフト作成
資料そのものではありませんが、完成した資料を送付する際のメール文や、関係者に協力を依頼する文章の作成もAIに任せれば効率的です。
指示の例: 「作成した〇〇の企画書を添付して、△△部長にアポイントを依頼するメールを作成してください。目的は予算の承認です。」
⚠️注意点: AIが生成した文章やデータは、必ず自分の目で事実確認(ファクトチェック)と、意図したニュアンスになっているかの最終調整を行うことが鉄則です。
おわりに -「伝わる文章」は、最強のビジネススキルになる
最後に、この教科書で学んだ、読み手を動かし「一発OK」を引き出す資料作成ライティングの要点を振り返ります。
- マインドセット: 主役は自分ではなく「読み手」。全ての文章は、相手の疑問に答え、相手をゴールまで導くためにある、という「読み手ファースト」を貫く。
- 3つの基本原則:
- ゴールから逆算する: 資料の「目的(相手にしてほしい行動)」を最初に決め、不要な情報を削ぎ落とす。
- 短く、具体的に書く: 一文を短くし、箇条書きや数字を多用することで、相手を疲れさせない。
- 話の地図を見せる: PREP法やアジェンダを活用し、読み手が常に話の現在地を理解できるようにエスコートする。
- AIの活用: AIを「優秀な副操縦士」と捉え、構成案の作成や文章の推敲・要約を任せることで、資料作成を高速化・効率化する。
どんなに優れたアイデアや分析も、相手に伝わらなければ存在しないのと同じです。逆に言えば、「分かりやすく伝える文章力」さえあれば、あなたの持つ価値を何倍にも増幅させることができるのです。
👉 まずは、明日作成する資料(あるいはメール1本)で構いません。 今日学んだテクニックのうち、たった一つでもいいので意識して使ってみてください。 「この一文は、もっと短くできないか?」そう考える癖をつけるだけでも、あなたの資料は昨日より確実に見違えるはずです。
「分かりやすい文章を書くスキル」は、一度身につければあらゆるビジネスシーンであなたを助けてくれる、一生モノの武器になります。
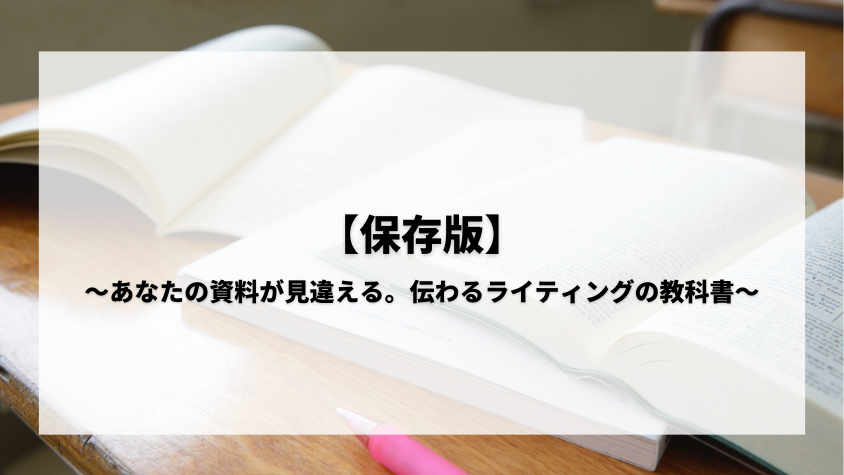
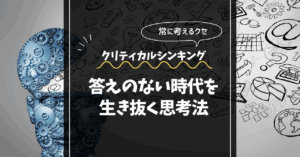
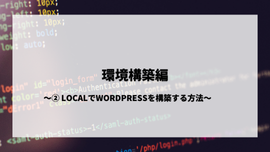
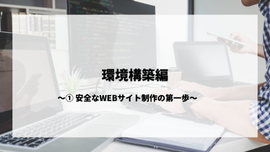

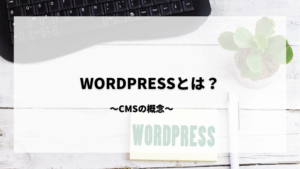
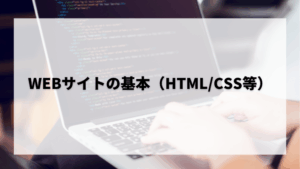
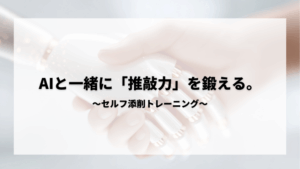
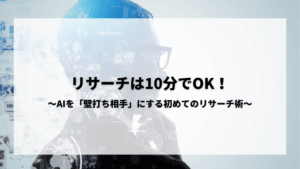
コメント