ランディングページの中でも、もっとも丁寧な設計が求められるのが Lモデル(Latent demand:潜在需要型) です。
このモデルは「読者がまだ自分では気づいていない不安や願望」を掘り起こし、その必要性を言語化した上で商品を提示します。
読者が「今のままでも問題ない」と思っている状態から、「実は放置するとリスクがある」「準備しておいた方が安心だ」と気づかせることが出発点です。その上で「解決策としてこの商品がある」と自然に導いていくのがLモデルの流れです。
特に保険・資産形成・教育・健康といった分野では、顧客がまだ自分の課題を明確に自覚していないケースが多いため、このLモデルが効果を発揮します。潜在層を顧客へと転換できる強力な型ですが、その分、丁寧な説明と信頼の積み重ねが欠かせません。
Lモデルの背景にある心理
Lモデルの根底には、読者がまだ自覚していない「潜在的な不安や欲求」を表面化させる、という考え方があります。
人は「現状に満足している」と思っていても、実際には将来の不安や漠然とした違和感を抱えていることが多いものです。ここに働きかけるのが、認知的不協和 と呼ばれる心理です。「自分の今の状態」と「本来あるべき状態」に差があると気づいた瞬間、人は強い緊張を覚え、そのギャップを埋めようと行動を起こします。
たとえば「今は収入に困っていないが、数年後に働き方が変われば不安定になるかもしれない」「体調は悪くないが、このまま何も対策をしなければ病気のリスクが高まるかもしれない」といった気づきは、読者の心に大きなインパクトを与えます。
Lモデルはこの「気づきを与える」プロセスを起点に、徐々に必要性を理解させ、解決策を提示し、行動に導いていきます。つまり、潜在層を顧客に変えるための教育型の構成 なのです。
Lモデルが効果を発揮するシーン
Lモデルは、顧客がまだ課題をはっきり自覚していない分野で特に効果を発揮します。読者に「今は大丈夫」と思わせている隠れたリスクや未来への不安を言語化することで、初めて「解決策が必要だ」と認識させられるからです。
代表的な領域としては、保険・資産形成・教育・健康 があります。
- 保険なら「万が一の時に家族を守れないかもしれない」
- 資産形成なら「老後の生活資金が足りなくなるかもしれない」
- 教育なら「子どもが将来選べる進路の幅が狭くなるかもしれない」
- 健康なら「今は元気でも、この生活習慣を続ければ病気のリスクが高まる」
このように「まだ顕在化していない問題」や「将来に備えるべきテーマ」に対して、Lモデルは強力なアプローチになります。
また、潜在層を顧客に変えるために丁寧な説明が必要なため、教育型コンテンツや長期的なブランド構築 とも非常に相性が良いのが特徴です。
Lモデルのメリットと限界
Lモデルの最大のメリットは、まだニーズが顕在化していない層を顧客に変えられる ことです。
すでに課題を認識している顕在層は、競合の商品やサービスも検討している可能性が高く、獲得競争が激しい傾向にあります。一方で潜在層は「まだ問題に気づいていない」ため、Lモデルで上手く教育できれば、競合が入る前に関係性を築き、自社の商品を第一選択肢として提示できます。
さらに、潜在層に働きかける構成は 市場そのものを広げられる 点でも大きな価値があります。保険や教育、健康習慣といった領域では、潜在需要を顕在化させることで新しい顧客層を掘り起こせるのです。ブランドやサービスを「啓発的な立場」で見せられるため、長期的な信頼関係を築く上でも有効です。
しかし一方で、Lモデルにはいくつかの限界があります。まず、説明が長くなりやすい という点です。潜在層に必要性を理解させるためには、問題提起から証拠、解決策まで丁寧に導かなければならず、自然と文章量が増えてしまいます。加えて、課題意識が薄い読者には「自分には関係ない」とスルーされやすいリスクがあります。さらに、問題を強調しすぎると「恐怖を煽られている」と感じさせ、信頼を損なう危険性もあるため、バランスが重要です。
Lモデルの構成ステップ
Lモデルは「まだ自分の悩みに気づいていない読者」を対象にしたLP構成です。
読者に違和感を気づかせ、必要性を理解させ、その上で商品を提示する流れが特徴です。
潜在層にアプローチするため、説明は丁寧に段階を踏む必要があります。
ステップ1:認知的不協和(気づかせる)
・目的:読者に「言われてみれば…」と現状の問題に気づかせる。
・要素:データ、統計、リスク提示/身近な例を用いた「将来の不安」
・テンプレ:「実は〈日常的な行動〉が〈大きなリスク〉につながっているのをご存じですか?」
・AI活用例:「20代会社員が副業をしないことで将来直面するリスクを5つ列挙」
ステップ2:必要性(必要と感じさせる)
・目的:問題を放置すると悪化することを理解させる。
・要素:放置コスト/将来の機会損失
・テンプレ:「このままでは〈未来の問題〉が避けられません。今こそ対策が必要です。」
・AI活用例:「副業を始めないことで10年後に起こりうる不利益を整理」
ステップ3:信用①(重みを示す)
・目的:問題提起に信憑性を持たせる。
・要素:第三者の調査データ/専門家の意見/事例
・テンプレ:「〈出典〉によれば、〈対象〉の〈割合〉が〈事実〉と報告されています。」
・AI活用例:「副業に関する統計データを一般読者にもわかりやすい一文に」
ステップ4:解決方法(道を教える)
・目的:商品を「潜在的な問題の解決策」として提示する。
・要素:シンプルな導入ステップ/ベネフィット中心の説明
・テンプレ:「この方法なら〈具体的課題〉を〈短期間〉で解決できます。」
・AI活用例:「副業未経験者がこのサービスで成果を出すまでの流れを3ステップで説明」
ステップ5:信用②(実績を示す)
・目的:商品の効果を補強する。
・要素:成功事例/数値データ/顧客の声
・テンプレ:「〈属性〉の〈氏名/匿名〉は〈期間〉で〈成果〉を達成しました。」
・AI活用例:「導入事例を成功ストーリーとして100字でまとめて」
ステップ6:比較(他と比べさせる)
・目的:現状維持や他の選択肢より合理的と納得させる。
・要素:現状 vs 商品 vs 他サービス の比較表
・テンプレ:「〈評価軸〉で比較すると、最短で〈望む状態〉に到達しやすいのは〈本商品〉です。」
・AI活用例:「現状維持、競合サービス、このサービスを比較して優位性を説明」
ステップ7:不安解消(不安を取り除く)
・目的:「自分にできるか?」という不安を払拭する。
・要素:FAQ/保証制度/サポート内容
・テンプレ:「もし〈懸念〉があっても、〈制度〉で安心して開始できます。」
・AI活用例:「潜在層が購入をためらう理由を10個挙げ、それぞれ安心させる回答を作成」
ステップ8:買う理由(納得させる)
・目的:「今、決断する理由」を与える。
・要素:特典/限定性/割引/時期的背景
・テンプレ:「〈期限〉までの申込で〈特典/割引〉。今が最も効率よく始められるタイミングです。」
・AI活用例:「今買うことを正当化する理由を5つ考えて」
ステップ9:行動を促す(前へ進ませる)
・目的:低ハードルで最初の行動を取らせる。
・要素:無料診断・相談・体験版などの一次CTA/本購入につなげる二次CTA
・テンプレ:「まずは〈無料の一歩〉から。所要〈時間〉、〈費用負担〉はありません。」
・AI活用例:「このサービスの低リスクCTAを10案」
まとめ:Lモデルは潜在層を顧客に変える教育型ルート
Lモデルは「まだ悩みに気づいていない読者」にアプローチできる唯一の型です。
現状に満足している層に 違和感を与え、必要性を言語化し、解決策と信頼を積み重ねて行動へ導く という教育的な流れを持ちます。
このモデルを使えば、保険・資産形成・教育・健康など、将来の備えや予防をテーマにした商品で 新規顧客層を掘り起こすことが可能 になります。短期的な成果よりも、中長期的な市場育成やブランド構築に適しているのも特徴です。
一方で、説明が長くなりやすく、煽りすぎると不信感を与えるリスクがあるため、AIを活用して「潜在的な不安を体系化」「FAQや保証を充実」「低リスクCTAを複数提示」する工夫が不可欠です。
Lモデルは、潜在層を顧客に育てるための教育型ルート。副業ライターが長期的に成果を上げるために必ず押さえておきたい構成 といえるでしょう。

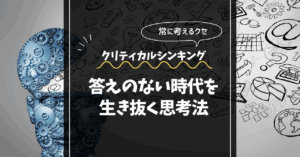
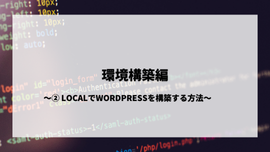
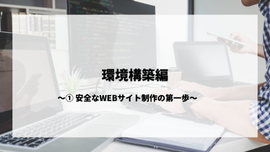

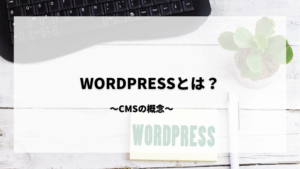
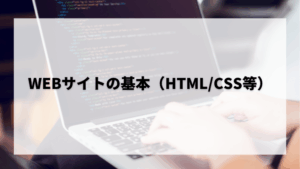
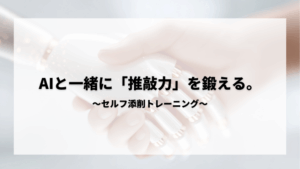
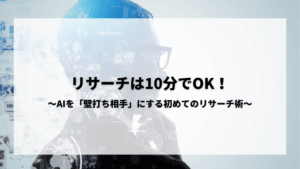
コメント