「文章は、書き終えてからが本当のスタートだ」
これは、多くのプロのライターが口にする言葉です。書いた文章を客観的に見直し、より分かりやすく、より心に響く言葉へと磨き上げていく作業、それが「推敲(すいこう)」です。
しかし、自分の文章の欠点というものは、なかなか自分一人では気づきにくいもの。かといって、毎回上司や同僚にレビューを頼むのも気が引けますよね。
そこで、このセクションでは、AIを「24時間いつでも付き合ってくれる、客観的で優秀な壁打ち相手」として活用し、あなた自身の「推敲力」を鍛えるためのセルフトレーニング方法を学びます。
AIからの多様な改善提案を取捨選択するプロセスを通して、あなたは良い文章の「型」を学び、自分の中に「編集者の視点」を育てることができるようになります。AIとの対話を通じて、文章のクオリティを自分自身で引き上げるスキルを身につけましょう。
トレーニングの「素材」を用意する
なぜ「自分の文章」で始めるのか?
推敲力を鍛える最も効果的な方法は、あなた自身が書いた、思い入れのある文章を素材にすることです。
なぜなら、自分が「何を伝えたかったのか」という意図を一番理解しているからです。AIからの改善提案に対して、「なるほど、その表現の方が自分の意図が伝わるな」あるいは「いや、AIの提案は論点がズレている」といった主体的な判断を下すことが、推敲力を鍛える上で最高のトレーニングになります。
お手本のような完璧な文章ではなく、少しでも「もっと上手く書けたらな」と感じたことのある、あなたのリアルな文章を用意しましょう。
【実践】トレーニング素材を選ぼう
あなたのPCやクラウドストレージの中から、直近1ヶ月以内に作成したビジネス文書を一つ、選んでみてください。
どんなものでも構いませんが、以下のようなものがトレーニングに適しています。
- 社内向けの報告書や日報
- (例:「〇〇プロジェクト 8月第4週 進捗報告」)
- 上司への提案や相談のメール
- (例:「件名:〇〇の件でのご相談」)
- クライアントへの企画提案書の冒頭部分
- (例:「拝啓 〇〇様、平素は格別のご高配を賜り…」から始まる文章)
- 社内チャットでの少し長めの連絡事項
選べましたか? もし適切なものがなければ、「あなたが上司に、新しい業務改善ツール(例えばChatGPT Businessプラン)の導入を提案するメール」を、今から5分程度で簡単に書いてみるのも良い演習になります。
素材の準備ができたら、いよいよAIとの対話を通じて、その文章を磨き上げていきます。 次のステップでは、AIに「優秀な編集者」になってもらうための最初のプロンプトを投げかけます。
AIに「編集者」として壁打ちを依頼する
漠然とした指示では、良い答えは返ってこない
AIに文章を改善してもらう時、多くの人がやってしまいがちな失敗が、「この文章を良くしてください」といった漠然とした指示を与えてしまうことです。これでは、AIも何に焦点を当てて改善すれば良いのか分からず、ありきたりな回答しか返ってきません。
重要なのは、AIに「どんな視点で文章をレビューしてほしいのか」を具体的に指示することです。今回は、AIに複数の役割を持った「優秀な編集者」になってもらいましょう。
AIに投げる「魔法の呪文(プロンプト)」
以下のプロンプトをコピーし、【ここにあなたの文章を貼り付け】の部分を、先ほどあなたが用意した文章に差し替えて、AIに入力してみてください。
【プロンプト】
あなたは、プロの編集者です。 私が書いた以下のビジネス文書について、改善点を指摘してください。
対象の文章
【ここにあなたの文章を貼り付け】
指示
以下の4つの観点から、具体的な改善案を提案してください。
- 明確化と簡潔化: より分かりやすく、簡潔にするための修正案を提示してください。特に、一文が長すぎる箇所や、曖昧な表現があれば指摘してください。
- トーンの調整: この文章の読み手(例:上司、クライアント)にとって、より丁寧で、説得力のあるトーンにするための修正案を教えてください。
- 表現のバリエーション: 使われている言葉や表現で、より効果的な言い換えがあれば、類語や別の表現を3つずつ提案してください。
- 修正版の提示: 上記の1〜3を総合的に判断し、あなたが考える最も優れた修正版の文章を一つ、提示してください。
【プロンプトのポイント】
- 多角的な視点を与える: 「明確化」「トーン」「表現のバリエーション」と複数の観点からレビューを依頼することで、AIは一つの正解に固執せず、多角的な改善案を提示してくれます。
- 思考プロセスを言語化させる: 単に修正後の文章だけを提示させるのではなく、なぜそう修正したのか(観点1〜3)を説明させることで、あなた自身が「なるほど、こういう視点で文章は改善できるのか」という学びを得られます。
- あなたの文章を「# 対象の文章」に入れる:
#をつけて項目を分けることで、AIはどこが対象で、どこが指示なのかを正確に認識しやすくなります。
さあ、プロンプトを投げたら、AI編集者がどんな回答を返してくるか見てみましょう。 次のステップでは、AIからの提案をどのように取捨選択し、自分のスキルとして吸収していくかを解説します。
AIの提案を取捨選択し、「推敲力」を吸収する
AIの答えは「正解」ではなく「提案」である
AIは素晴らしい改善案を提示してくれますが、その全てが100%正しいとは限りません。なぜなら、AIはあなたの文章の本当の意図や、相手との関係性、その場の微妙なニュアンスまでは完全に理解しているわけではないからです。
ここで重要なのは、AIの提案を鵜呑みにするのではなく、あなたが「最終的な編集長」として、どの提案を採用し、どの提案を不採用にするか、主体的に判断することです。この取捨選択のプロセスこそが、あなたの推敲力を飛躍的に向上させます。
【実践】3つの問いで、提案を吟味しよう
AIから提示された改善案(特に「4. 修正版の提示」で示された文章)を元の文章と見比べながら、以下の3つの問いを自分に投げかけてみましょう。
問い1:伝えたい本来の意図やニュアンスは保たれているか?
- チェックポイント:
- 簡潔になった結果、必要な情報や丁寧さが失われていないか?
- 表現が綺麗になったことで、逆に自分の言葉としての熱意や個性が消えてしまっていないか?
思考の例: 「確かにAIの修正案はスッキリして分かりやすいけど、クライアントとの関係性を考えると、元の少し丁寧すぎるくらいの表現の方が安心感を与えられるかもしれないな。ここはあえて元の表現を残そう。」
問い2:なぜAIは、このような修正を提案したのか?
- チェックポイント:
- AIが「一文が長い」と指摘した箇所は、確かにもう一度読まないと理解しにくいか?
- AIが提案した別の表現(類語)の方が、より具体的で誤解を生まないか?
思考の例: 「なるほど、自分では普通に使っていた『〜的な』という言葉が、AIに『曖昧な表現』と指摘されたな。確かに『具体的な』と言い換えた方が、意図が明確に伝わる。これは今後の文章でも意識しよう。」
問い3:この改善パターンは、他の文章にも応用できるか?
- チェックポイント:
- 今回のAIの提案から、汎用的な「型」や「ルール」を見つけ出せないか?
思考の例: 「AIは、文章の冒頭に必ず『結論』を持ってくるように修正しているな。これは、第2章で学んだPREP法と同じだ。報告書でもメールでも、まず結論から書くことを徹底するだけで、伝わり方が変わりそうだ。」
この3つの問いを通してAIの提案を吟味し、最終的なアウトプットを完成させれば、トレーニングは終了です。 このプロセスを繰り返すことで、AIが指摘してくれた改善パターンがあなたの中に蓄積され、やがてAIの手を借りずとも、自分自身で多角的な視点から文章を推敲できるようになります。
以上で、セルフ添削トレーニングは終了です。お疲れ様でした!
次のセクションでは、いよいよ総仕上げです。これまで学んだリサーチ術と推敲力を組み合わせ、AIと協業して一つのビジネス文書をゼロから作り上げる総合演習に挑戦します。
まとめ:AIは、あなたの「推敲力」を鍛える最高のパートナー
このセクション「AIと一緒に「推敲力」を鍛える。セルフ添削トレーニング」では、AIを客観的な編集パートナーとして、自分自身の文章を改善していく具体的なプロセスを学びました。
ここでの重要なポイントを振り返りましょう。
- 最高の素材は「自分の文章」: 伝えたい意図や背景を最も理解しているあなた自身が、AIの提案を吟味することで、学びは最大化されます。
- AIには「多角的な編集者」になってもらう: 「良くして」という曖昧な指示ではなく、「簡潔に」「別の表現で」といった具体的な視点を与えることで、質の高い改善案を引き出せます。
- あなたが「最終編集長」になる: AIの提案はあくまで「たたき台」です。その提案の意図を汲み取り、採用・不採用を判断するあなたの思考プロセスこそが、「推敲力」を直接鍛えるトレーニングになります。
このトレーニングの最終ゴールは、AIの助けがなくても、あなたの中に「客観的な編集者の視点」を育てることです。AIとの壁打ちを繰り返すことで、良い文章のパターンが自然と身につき、書く文章の質が着実に向上していきます。
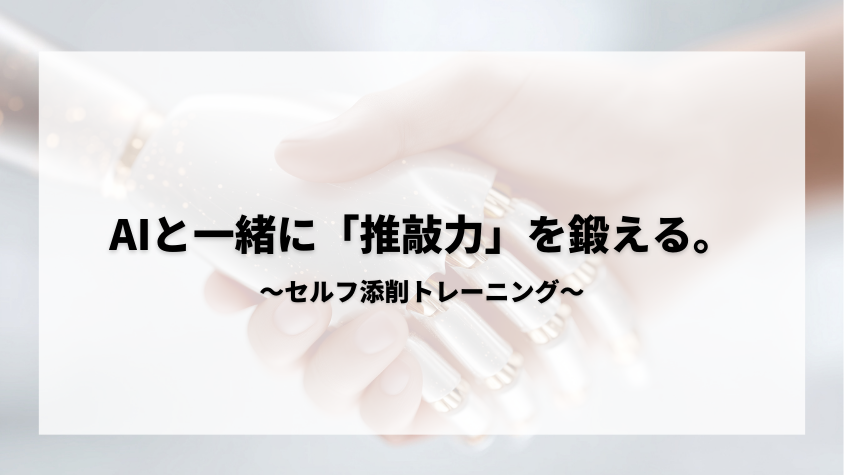
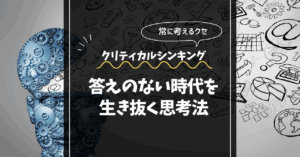
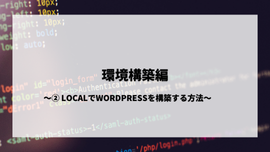
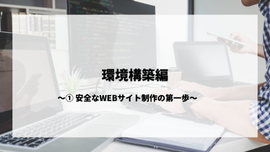

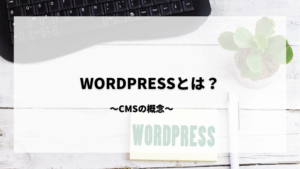
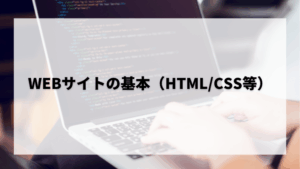
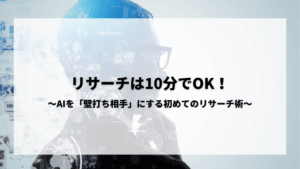
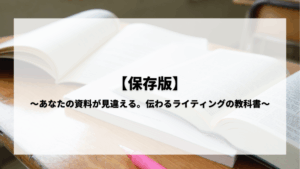
コメント