「やりたいことがわからない」
そう感じたとき、私たちはつい「何か新しいことを始めなきゃ」「スキルを身につけなきゃ」と考えがちです。本屋に並ぶ「やりたいことの見つけ方」といった本を手に取ったり、様々な人の成功事例を調べたりするかもしれません。
でも、どれだけ情報を集めても、なぜか心は満たされない。漠然とした焦りや不安だけが、日に日に大きくなっていく。
それはなぜでしょうか?
もしかしたら、あなたは「Do(何をやるか)」や「Have(何を手に入れるか)」から答えを探そうとして、本当の自分を見失っているのかもしれません。
コーチングでは、まず「Be(どうありたいか)」から始めます。自分がどんな人間でありたいのか、どんな価値観を大切にしたいのか。この「あり方」を深く掘り下げることで、あなたの人生の羅針盤が明確になります。
そして、その羅針盤が指し示す方向へ向かうための「行動(Do)」と、その結果として「手に入るもの(Have)」が、自然と見えてくるのです。
外に答えを探すのはやめて、一度立ち止まってみませんか?あなたの答えは、あなたの中にあります。
なぜ、私たちは「Have」を追い求めてしまうのか?
「いい大学に入って、いい会社に就職すれば幸せになれる」
多くの日本人が、幼い頃からそう教えられてきました。それは単なる思い込みではなく、日本が歩んできた歴史と社会の流れの中で培われた価値観と言えるでしょう。
戦後の日本は、焼け野原から奇跡的な経済成長を遂げました。その過程で人々が追い求めたのは、テレビや洗濯機、自動車といった「三種の神器」と呼ばれるモノでした。つまり、モノを手に入れることがそのまま幸福と結びつく時代があったわけです。
こうした背景が、やがて「安定した学歴や職業=安心と幸せ」という考え方を強固にしていきました。今もなお、多くの人が無意識のうちに「Have(所有)」を基準に幸せを測ってしまうのは、その歴史的な土台が影響しているからです。
では、時代ごとにどのように価値観が変わっていったのでしょうか?
戦後〜高度経済成長期
戦後の日本は、文字通り「焼け野原」からの再出発でした。人々の最優先課題は、生き延びるための衣食住を満たすこと。食べ物や住まい、最低限の生活基盤を確保することが幸福の条件でした。
その後、高度経済成長期に入ると状況は大きく変わります。経済が右肩上がりで成長し、家電や自動車といった新しい製品が次々と登場しました。特にテレビ・洗濯機・冷蔵庫は「三種の神器」と呼ばれ、これらを持つことが一家の豊かさや社会的成功の象徴とされました。
当時の人々にとって、モノを所有することは単なる便利さ以上の意味を持っていました。それは「生活が向上している」という実感であり、「家族を守れている」という安心感でもあったのです。言い換えれば、Have(何を持っているか)=幸せという方程式が、国民全体に深く刷り込まれた時代だったと言えます。
この「所有こそが幸福の証」という考え方は、やがて教育や社会制度を通じて次の世代にも受け継がれていきます。こうして、「より多くを持つことが豊かさにつながる」という価値観は、日本人の無意識の中に強く根付いていきました。
バブル期〜「安定神話」の誕生
高度経済成長期に築かれた「モノを持つことが幸せ」という価値観は、バブル期にさらに強化されていきました。企業は好調で、新卒で大手企業に入社すれば、定年まで雇用が守られる「終身雇用」と、年齢とともに給料が上がる「年功序列」の仕組みが当たり前でした。
この仕組みは、人々に大きな安心感を与えました。「いい大学に入り、いい会社に就職すれば一生安泰」という考えが、社会全体に広く浸透していったのです。親世代は子どもに「とにかく勉強して良い大学に」と強く求め、教育もまた「安定した職業に就くこと」をゴールに据えていました。
結果として、「学歴→大企業→安定収入」という一本道が、成功や幸せの「正解」とされるようになります。これは言い換えれば、Have(安定した収入や地位)を手に入れることで幸せになれるという「安定神話」が完成した時代でした。
人々は疑うことなくこのレールを歩もうとし、社会全体もその価値観に合わせて動いていました。大学進学率の上昇、企業の就職人気ランキング、住宅ローンを組んでマイホームを購入すること…。そのすべてが「安定=幸福」という方程式を裏付けていました。
バブル崩壊と価値観の揺らぎ
1990年代に入り、バブル経済が崩壊すると、それまで盤石だと思われていた「安定神話」は大きく揺らぎ始めました。大企業であっても経営不振に陥り、リストラや早期退職が相次ぎます。これまで「一度入社すれば定年まで安泰」と信じられていた終身雇用制度が、実は絶対ではなかったことが明らかになったのです。
また、バブル崩壊の影響を強く受けたのが就職氷河期世代です。たとえ大学を卒業しても、希望する企業に就職できない若者が溢れ、「いい大学→いい会社→安定」というレールが機能しなくなっていきました。
それでも親世代や学校教育は、戦後から続く価値観を手放せず、「とにかく安定した仕事に就くことが大切」というメッセージを発信し続けました。その結果、若い世代の多くは「安定を追い求めても報われない現実」と「安定こそ正しいという刷り込み」の狭間で葛藤することになります。
つまり、バブル崩壊以降の日本は、Haveを追いかけても必ずしも幸福につながらない時代に突入しました。しかし社会や文化の深層には、依然として「所有や安定が幸せをもたらす」という価値観が根強く残っていたのです。
現代とグローバル比較
バブル崩壊から数十年が経ち、日本社会は依然として「安定志向」を色濃く残しています。親世代から受け継いだ「いい大学に入って、いい会社に就職すれば安心できる」という考え方は、今も教育や進路指導の中で根強く語られています。
しかし現代を生きる私たちは、その価値観だけでは満たされない現実に直面しています。終身雇用は事実上崩壊し、将来が約束されるキャリアパスはほとんど存在しません。むしろ「安定を選んだはずなのに不安が消えない」と感じる人も少なくありません。
一方で、海外に目を向けると価値観の基準は大きく異なります。欧米の先進国では、すでに物質的な豊かさがある程度前提となっているため、人々は「どうありたいか(Be)」「どんな経験をしたいか(Do)」を重視する傾向が強いのです。キャリアも「安定」より「やりがい」や「社会的意義」を軸に選ぶ人が多く、ライフスタイルの多様性も当たり前に受け入れられています。
日本でも、その影響を受けて価値観の変化が起きつつあります。特にZ世代を中心に「モノよりも経験」「安定よりも自分らしさ」を大切にする動きが広がり、SNSや副業の普及によって自己表現や新しい働き方を模索する人が増えています。
つまり、「いい大学に入れば幸せになれる」という価値観は、ある時代においては確かに有効でしたが、今の時代には必ずしも通用しません。これからは、過去から受け継いだ「Have」の基準に縛られるのではなく、自分自身の「あり方(Be)」を軸に人生をデザインしていくことが求められているのです。
「Be・Do・Have」のサイクルを逆転させる
私たちはつい「欲しいもの(Have)」を出発点に人生を考えてしまいます。
「年収1,000万円を手に入れる」「マイホームを購入する」「昇進して肩書きを得る」──こうした目標は確かに魅力的に見えますが、そのためにどんな行動をし、最終的にどんな自分になりたいのかを深く考えることは少ないのではないでしょうか。
しかし、この順序ではどれだけ達成しても心から満たされないケースが多く見られます。なぜなら、行動の動機が「他人の評価」や「物質的な所有」といった外的な要因にあるためです。
コーチングの考え方では、このサイクルを逆転させます。
出発点を「Have」ではなく、「Be(どうありたいか)」に置くのです。
一般的なサイクル(Have → Do → Be)
- Have:年収1,000万円を手に入れる
- Do:そのために長時間労働や資格取得に励む
- Be:結果として幸せな自分になる(はず)
→ 外的基準に振り回され、達成しても満たされにくい
コーチング的なサイクル(Be → Do → Have)
- Be:自分は「人を支える存在でありたい」
- Do:そのためにコーチングを学び、実践する
- Have:結果として「人の挑戦を応援できる仕事」や「成長実感」が手に入る
→ 内的基準から行動が生まれるので、達成感が深い
ポイント
逆に「Have」を先にすると、行動が苦しくなり、幸せが遠のく…々の夢を応援する役割(Have)」という、心から満たされる未来が手に入るでしょう。
出発点が「外の基準」か「自分の基準」かで、満足感は大きく変わる
「Be」を明確にすると、自然に「Do」と「Have」がついてくる
人生を設計するときに、「何を手に入れるか」よりも「どうありたいか」を問い直すこと。
これこそが、心から満たされるためのサイクルを回す第一歩です。
マズローが教えてくれる、人生の羅針盤
「やりたいことがわからない」という悩みは、心理学者のアブラハム・マズローが提唱した「欲求5段階説」に照らし合わせると、より深く理解できます。マズローは、人間の欲求には階層があり、低次の欲求が満たされると、人は高次の欲求を満たそうとすると考えました。
Licensed by Google
欲求5段階説とは
マズローが提唱した「欲求5段階説」は、人間の欲求をピラミッド型に整理したものです。特徴は、下位の欲求が満たされると、次の高次の欲求へと進んでいくという点にあります。私たちの行動や悩みの多くは、この階層のどこにいるかによって説明できるのかもしれません。
- 生理的欲求
食事・睡眠・排泄など、生命を維持するために欠かせない最も基本的な欲求。
(例:お腹が空いているときは勉強や仕事どころではない) - 安全の欲求
衣食住が安定し、身体的・経済的に安心して暮らせる状態を求める欲求。
(例:収入の安定、住む場所がある、健康が守られる) - 社会的欲求(所属と愛の欲求)
家族・友人・恋人・職場など、何らかの集団に属したい、愛し愛されたいという欲求。
(例:仲間がほしい、孤独ではなくつながりを感じたい) - 承認欲求
他人から認められたい、尊敬されたいという欲求。
(例:評価されたい、出世したい、SNSで「いいね」が欲しい) - 自己実現欲求
自分の能力や可能性を最大限に発揮し、「自分らしく生きたい」と願う欲求。
(例:本当にやりたいことに挑戦する、自分の理想の姿を追求する)
この理論のポイントは、下位が満たされないと上位に進めないということです。
例えば、生活が不安定なときに「自己実現」を考えるのは難しいでしょう。逆に、基盤が安定している現代の私たちは、承認や自己実現といった上位欲求で悩みやすい傾向にあります。
「やりたいこと」はどの段階にある?
現代の日本社会では、すでに多くの人が下位の欲求──「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」──をある程度満たしています。衣食住に困らず、一定の人間関係を築けている人が大多数でしょう。
そのため、「やりたいことが見つからない」と悩む人の多くは、4の承認欲求と5の自己実現欲求の間で葛藤しているケースがほとんどです。
承認欲求の段階では、どうしても他人の目や社会的な評価を基準に「やりたいこと」を探してしまいます。
- 「人から褒められる仕事」
- 「収入や肩書きで認められる働き方」
- 「安定した大企業に入ること」
これらは一見「やりたいこと」のように思えますが、実際には「他人に認められるための手段」であることが多いのです。
一方、マズローが強調した自己実現欲求は、自分自身の内側から湧き上がる「Be(どうありたいか)」 に基づいた行動です。
- 「自分の強みを活かして挑戦したい」
- 「人の役に立つことで充実感を得たい」
- 「本当に心から大事にしたい価値観に沿って生きたい」
この段階にシフトすることで、初めて「心から満たされるやりたいこと」に出会えるでしょう。
まずは、価値観を深く掘り下げてみよう
自己実現のスタート地点は「やりたいこと」を探すことではなく、自分の価値観を知ることです。
価値観とは、あなたが「これは大事にしたい」と心から思える基準であり、行動や判断の軸になるもの。逆に言えば、価値観が見えなければ「やりたいこと」を考えても、どこか他人基準のままになりがちです。
そこで役立つのが、これまでの経験を手がかりに価値観を深掘りするワークです。
過去の「喜び」から価値観を探る
これまでの人生を振り返って、心から嬉しかった瞬間や夢中になった体験を思い出してみましょう。
- プロジェクトを成功させたとき → 「協力して目標を達成すること」に価値を感じている
- 誰かの相談に乗って感謝されたとき → 「人の役に立つこと」に喜びを感じている
ポジティブな体験は、あなたの本質的な価値観を映し出しています。
怒りや嫌悪感から「譲れないもの」を見つける
次に、強い怒りや嫌悪感を抱いた出来事を思い出してみましょう。そこには、あなたが大切にしているのに侵された「譲れない価値観」が隠れています。
- 頑張っている仲間が正当に評価されなかった → 「公平性」「努力が報われること」を重視している
- 無責任な態度を取る人を見た → 「誠実さ」「責任感」を大切にしている
ネガティブな感情も、実は自分の価値観を知るための大きなヒントになります。
ワークのゴール
喜びや怒りの両面から浮かび上がる共通点が、あなたの「核となる価値観」です。
これこそが、あなたの 「あり方(Be)」を形づくる土台 になります。
「やりたいことがわからない」と悩むときは、スキル探しや情報収集よりも、まず自分の価値観を丁寧に掘り下げること。そこから自然に「やりたいこと(Do)」や「手に入るもの(Have)」が見えてきます。
結論:一人で抱え込まないという選択
ここまでで、「やりたいことがわからない」という悩みの背景と、その突破口が「価値観の掘り下げ」にあることを見てきました。とはいえ、実際に自分ひとりで価値観を深く探るのは簡単なことではありません。思考が堂々巡りになったり、「これが本心なのか、それとも他人の期待なのか」と迷ってしまうことも少なくないでしょう。
だからこそ大切なのは、一人で抱え込まないことです。
コーチングのサポート
コーチングは、対話を通じて「自分の中にある答え」を引き出すための仕組みです。質問やフィードバックを受けながら、曖昧だった価値観や「あり方(Be)」を言語化できるので、自己理解が格段に深まります。
生成AIという新しい相棒
また近年では、生成AIを活用することで、自分の思考を整理したり、アイデアを広げたりすることも可能になっています。AIに問いかけることで、自分一人では気づかなかった価値観や視点が浮かび上がることもあるのです。
「もっと自由に表現したい」「自分らしい価値を見つけたい」という想いがあるなら、AIは強力な相棒になってくれるでしょう。
最後に
「やりたいことがわからない」という悩みは、決してマイナスではありません。それは、他者からの承認を基準にした生き方から、自分自身の「あり方」を基準にした生き方へとシフトするための、人生の転換点なのです。
あなたの「答え」は外側にはありません。
内側に眠っている価値観を掘り起こし、誰かやAIと対話しながら少しずつ形にしていくこと。それが、心から納得できる「やりたいこと」につながっていきます。
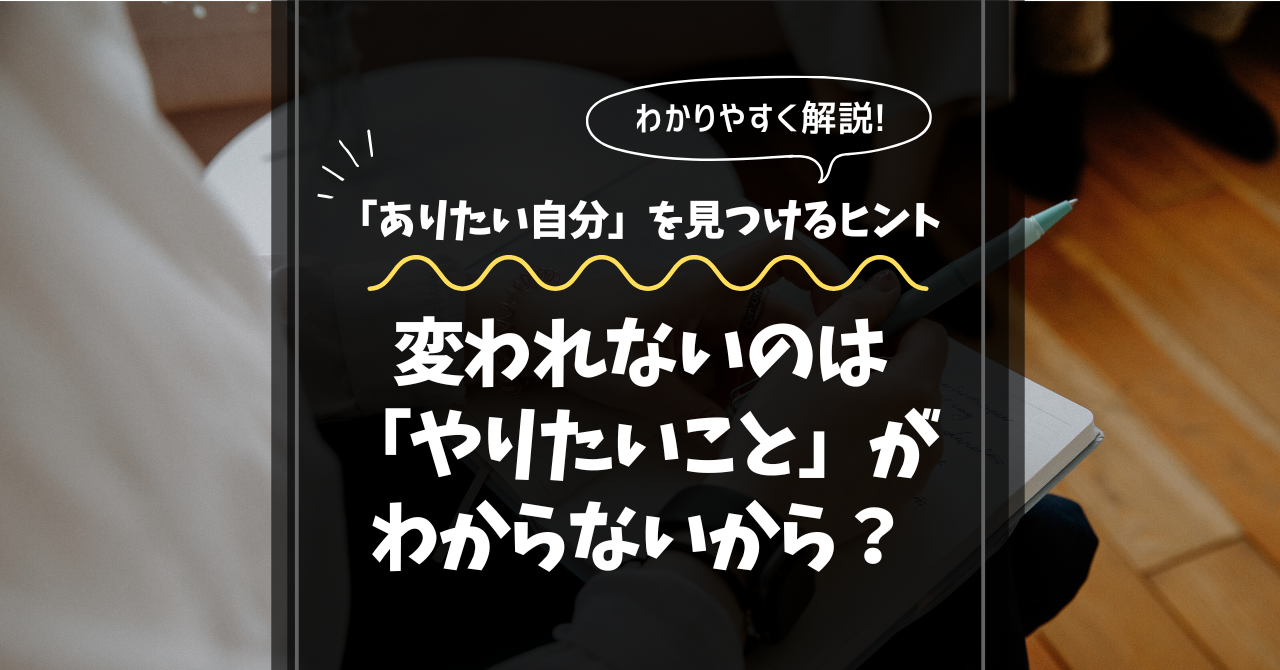
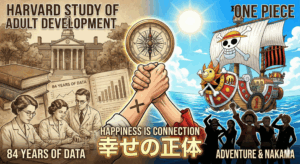
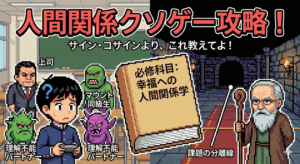
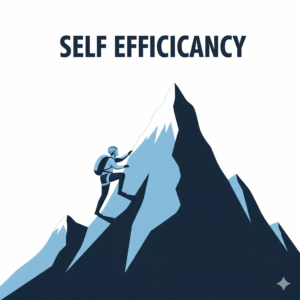
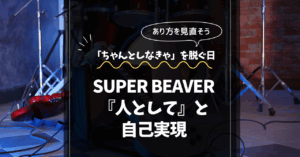
コメント