AIに「〇〇を作って」とお願いしたら、思っていた形と違うアウトプットが出てきた――。
そんな経験はありませんか?
これはAIが悪いわけではなく、私たちが「どんな形式でほしいか」を伝えていないから。
たとえるなら「ドリンク補充して」と曖昧に頼むと、期待とは違う飲み物が届くのと同じです。
生成AIをうまく活用する秘訣は、出力形式を決めること。
この記事では、議事録を題材にしながら、AIに“いい型”を出させ、選び取り、標準化していくプロセスを紹介します。
出力形式はなぜ「命」なのか
生成AIを実務で使ってみると、もっとも悩まされるのは 「そのままでは使えない出力」 です。
同じ依頼をしても毎回フォーマットが違い、欲しい情報を探すのに時間がかかったり、結局人が整形し直すことになります。
ここで重要なのは、正確性よりもまず形式の一貫性です。
多少の誤りや抜けがあっても、決まったフォーマットに収まっていれば修正は容易です。
逆に形式が揺れていると、毎回ゼロから再構成する必要があり、手間もストレスも増えてしまいます。
さらに、出力形式をあらかじめ定めておくことで、AI自身も焦点を絞りやすくなります。
どんな粒度で、どんな順序で、どんな枠組みに沿ってまとめればよいのかが明確になるため、結果的にアウトプットの質も安定してきます。
つまり、生成AIを業務で「本当に使える」ものにするためには、出力形式の設計こそが命なのです。
出力形式を指定するとは? ― ドリンク補充の比喩
出力形式の重要性をもっと身近な例で考えてみましょう。
たとえば、オフィスで「ドリンクを補充して」とだけ頼んだとします。
- この場合、持ってこられるのは水かもしれないし、お茶かもしれない。
- 時には炭酸飲料や甘いジュースが並ぶこともあるでしょう。
- 確かに「ドリンク」ではあるけれど、本当に欲しかったものとは限りません。
一方で、こう頼んだらどうでしょう。
- 「スポーツドリンクを6本補充してください」
→ 必要なものが、必要な数だけ、確実に届きます。
この違いはそのまま生成AIに当てはまります。
「議事録を作って」と曖昧に頼めば、毎回出力形式がばらばらになり、使いづらい結果が返ってきます。
逆に「議題・決定事項・アクションを見出し付きでまとめて」と指定すれば、欲しい形で安定したアウトプットが得られるのです。
議事録で学ぶフォーマット設計
出力形式の重要性をもっとも実感できる題材のひとつが、議事録です。
同じ会議をまとめても、形式が違えば「使いやすさ」が大きく変わります。
議事録の基本タグ(見出し)
最低限押さえるべき要素は次の5つです。
- メタ情報(会議名・日時・出席者など)
- 議題(アジェンダ)
- 議事内容(発言の経緯や要点)
- 決定事項(会議で決まったこと)
- アクションアイテム(誰が何をいつまでにやるか)
2つの代表的フォーマット
- ミニマム型(確認用)
- 決定事項とアクションだけに絞る。
- 会議後に素早く共有したいときに最適。
- フル型(正式記録用)
- 議事内容を含めて詳細に残す。
- 後で経緯を振り返る必要があるときに有効。
サンプル(ミニマム型)
# 議事録
会議名: ○○プロジェクト定例
日時: 2025年8月29日
出席者: A, B, C
## 決定事項
- リリースは10月中旬
- 結合テストは9月実施
## アクションアイテム
- [ ] A: テスト環境準備(〜9/10)
- [ ] B: 結合テスト計画作成(〜9/5)
議事録フォーマット例(フル型:正式記録用)
# 議事録
会議名: ○○プロジェクト定例MTG
日時: 2025年8月29日 10:00〜11:00
場所: Zoom
出席者: A, B, C
---
## 議題
1. プロジェクト進捗
2. リリース計画
3. 次回の課題
---
## 議事内容
### 議題1: プロジェクト進捗
- A: 開発は予定通り進行中
- B: テスト環境は9月上旬に準備予定
### 議題2: リリース計画
- C: リリースは10月中旬を目指す
- 決定: 9月に結合テストを実施
### 議題3: 次回の課題
- A: ドキュメント整理の遅れあり
- B: 対応方針を次回までに検討
---
## 決定事項
- リリースは10月中旬に行う
- テスト環境は9月上旬までに整備
## アクションアイテム
- [ ] B: テスト環境準備(〜9/10)
- [ ] C: 結合テスト計画作成(〜9/5)
- [ ] A: ドキュメント整理(〜9/12)
出力形式をAIで探す ― ガチャ的アプローチ
「どんなフォーマットが一番使いやすいのか?」
これは頭の中で考えても、なかなか答えは出ません。
むしろ悩むよりも、まずAIに出力させてみた方が早い。
生成AI、特にChatGPTには“ガチャ性”があります。
同じ依頼でも、再出力ボタンを押すだけで、形式やまとめ方が微妙に変わる。――まるでガチャを回しているかのように、異なるパターンが次々と得られるのです。
この性質を「不安定さ」と捉えるのではなく、「発想の幅」として活かすことが重要です。
AIに複数の型を出させ、それを比べ、最も使いやすいものを選び取る。
そして選んだ型を標準フォーマットとして定着させれば、毎回バラつくアウトプットを逆に安定した生産性につなげられます。
一方で、Geminiのように答え方の多様性が出にくいモデルもあります。
その場合は再出力だけではなく、条件を変えて意識的にバリエーションを引き出す工夫が必要です。
出力形式をAIで探すステップ
ステップ1. まずは出力させる
- シンプルに「議事録を作って」と依頼。
- 完成品を求めるのではなく、フォーマットのたたき台を得ることが目的。
ステップ2. ガチャを回す(再出力)
- ChatGPTなら「再出力」ボタンを押すだけで微妙に構成が変わる。
- まずは数パターンを並べて“AIがどんな型を出すか”を観察する。
ステップ3. バリエーションを広げる(タグ=見出しを調整)
AIの出力は、どんな見出し(タグ)を指定するかで大きく変わります。
ここを工夫することで、求めるフォーマットに近づけることができます。
例えば:
# 出力形式
## 議題
## 議事内容
## 決定事項
### ①
### ②
### ③
- 大見出し(##) に「議題」「議事内容」「決定事項」を置くと、全体の枠組みが整理される。
- 小見出し(###) を番号付きにすれば、決定事項が一覧性を持って並ぶ。
- 「## 要約」「## 詳細」「## タスク」と置き換えれば、報告書やレポートにも応用可能。
👉 タグの調整は「情報の粒度」と「読みやすさ」を左右する核心部分。
ここをいじるだけで、AI出力の型は大きく変わるのです。
ステップ4. 並べて比較する
出力を比べて「丸ごとどれかを採用」するのではなく、良い部分だけを抜き出してブレンドする。
- A案の「決定事項の並べ方」
- B案の「アクションのチェックリスト」
- C案の「議事内容の粒度」
👉 “合成”することで、自分やチームに最適なフォーマットに近づける。
ステップ5. 標準フォーマットに採用する
👉 ポイントは、「悩む前にAIに出力させる」→「ガチャで揺らす」→「タグ設計で整える」 という流れ。
これで、ただのバラつきを「型の発見プロセス」に変えられます。
実務への落とし込み
ここまで見てきた「出力形式の設計」を、実務の中に落とし込むにはどうすればいいか。
ポイントはシンプルに ルール化・共有・徹底 の3つです。
チームで「必須見出しルール」を決める
- 議事録なら「## 議題」「## 決定事項」「## アクションアイテム」だけは必須にする。
- 提案書なら「## 背景」「## 提案内容」「## 次のアクション」を必須にする。
👉 どんなドキュメントでも「最低限そろえる枠」を先に決めてしまえば、迷いがなくなる。
フォーマットをテンプレ化して共有
- チームのNotionやGoogleドキュメントにテンプレートを保存。
- 「この見出し構造を使う」と全員で合意しておけば、誰が作っても同じ形で出てくる。
👉 テンプレートは“チーム共通の型”として扱うのがコツ。
AIには「必ずこの形式で」とプロンプトに書き込む
- 例:「以下の見出し構造に従って議事録を作成してください」
- 人が後から整えるよりも、AIに最初から型に沿わせる方が効率的。
👉 ルールをAIに伝えることが、安定した出力の第一歩。
まとめ:生成AI活用の秘訣は「出力形式」にあり
生成AIを業務で本当に活かすには、内容の正確さよりもまず 形式の一貫性 が決定的に重要です。
形式が整っていれば、多少の誤りは直せるし、成果物としてすぐに使える。
逆に形式がバラバラでは、毎回ゼロから手直しが必要になり、効率は一気に落ちてしまいます。
議事録の例で見たように、
- ミニマム型でスピード共有
- フル型で正式記録
といった使い分けも、結局は「出力形式をどう設計するか」に帰結します。
その形式を決める最短の方法が、AIの“ガチャ性”を逆手に取るアプローチです。
いくつかの出力を試し、良い部分を拾って混ぜ、標準フォーマットに落とし込む。
そしてチームで必須見出しをルール化し、AIに「必ずこの形式で」と伝える。
ドリンクを補充してもらうときに「なんでもいい」と頼むか、「スポーツドリンクを6本」と指定するかで結果が変わるように、
生成AIも「形式を指定するかどうか」で使える成果物になるかどうかが決まります。
出力形式は命。
形式を設計することが、生成AIを“便利なおもちゃ”から“業務の武器”に変える秘訣です。
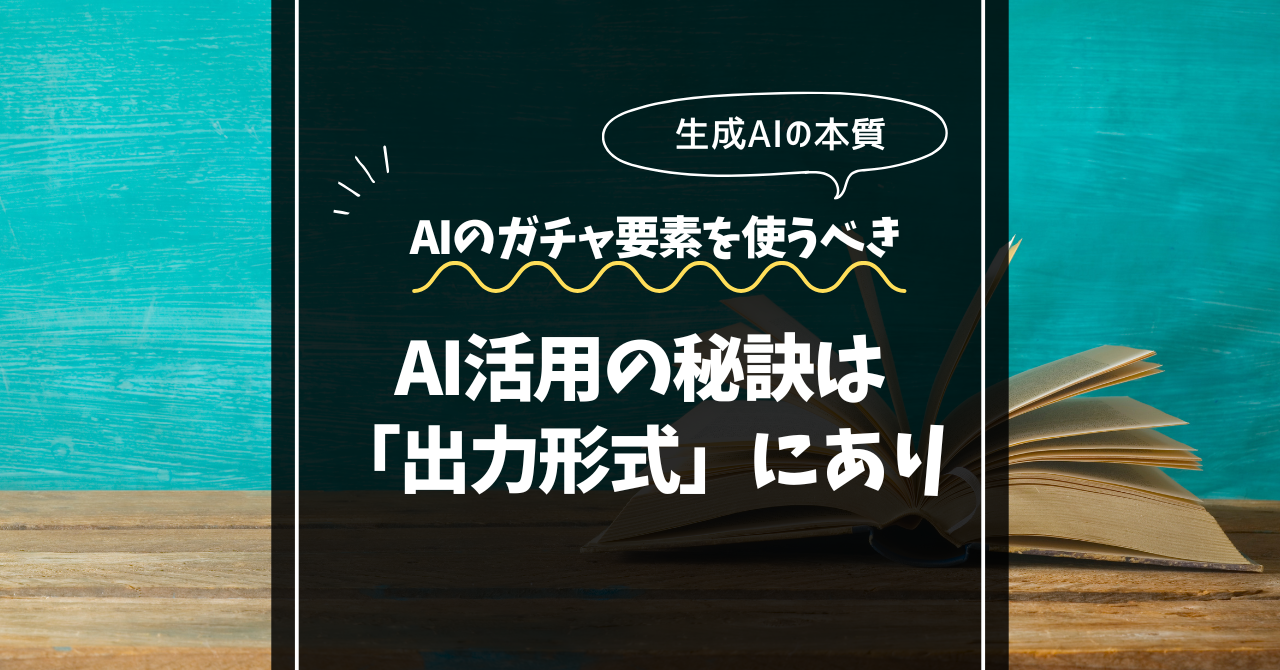
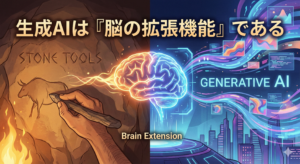

コメント