副業ライターにありがちな失敗は、「とにかく思いついたことから書き始めてしまう」ことです。
これでは内容が整理されず、読者にとって読みにくい文章になりがちです。
実務で求められるのは、短時間で分かりやすく、説得力のある文章。そのためには「型=文章構成」を理解し、自在に使いこなせることが欠かせません。
幸いなことに、生成AIを活用すれば同じテーマを PREP法・SDS法・ストーリー構成 など複数の型で出力させ、違いを比較しながら学ぶことができます。これにより「構成の型を体感で理解する」練習が効率的にできるのです。
ここでは代表的な3つの構成を取り上げ、それぞれの特徴とAIを使った学び方を見ていきましょう。
なぜ構成が重要なのか
文章は「何を書くか」だけでなく、「どう並べるか」で伝わり方が大きく変わります。
同じ情報でも、順序や組み立て次第で「伝わる文章」にも「読みにくい文章」にもなるのです。
副業案件では特に、短時間で読者に理解してもらうことが求められます。
- LPや広告コピーでは「結論から提示」して説得する必要がある
- SEO記事では「要点を整理」して、離脱されずに最後まで読ませる必要がある
- SNSや動画台本では「ストーリー性」で感情を動かすことが重要になる
つまり、構成を知らずに書くのは「地図なしで旅をするようなもの」。ゴールにたどり着けるかどうかは運次第になってしまいます。
生成AIを使えば、同じテーマを複数の構成で出力させることができるので、「型による違い」を比較しながら学習することが可能です。これにより、実践を通じて自然に構成力が身につきます。
PREP法(結論 → 理由 → 具体例 → 再結論)
PREP法は、文章を「短く・わかりやすく・説得力を持たせて」伝えるための最強テンプレートです。特に副業ライターにとっては、LP・営業資料・広告コピーなど成果を求められる案件で即効性がある型と言えます。
PREP法の基本構造とポイント
- Point(結論)
- 文章の最初に「結論」を置くことで、読み手の注意を一瞬で引きつける。
- 忙しい読者は冒頭で「読む価値があるか」を判断するため、結論から提示するのが鉄則。
- コツ:短く端的に言い切る。「〜です」「〜しましょう」など断定形で。
- Reason(理由)
- 結論を支える「根拠」を示すパート。
- 読者に「なるほど、それなら確かに」と納得してもらう。
- コツ:理由は1つでもよいが、2〜3個あると説得力が高まる。
- Example(具体例)
- 読者がイメージできる事例やデータを提示して、信頼性を補強する。
- コツ:実際の数字や体験談を使うと説得力が格段に上がる。
- 副業案件で有効な切り口:成功事例・導入効果・比較データ
- Point(再結論)
- 最後にもう一度「結論」を提示して、読者の記憶に残す。
- コツ:「だから〜すべきです」「今すぐ〜しましょう」と行動を後押しする形に。
PREP法が効果的なシーン(副業案件での具体例)
- LP(ランディングページ)
- Point:「この商品はあなたの悩みを解決します」
- Reason:「理由は、専門家監修の◯◯成分を配合しているからです」
- Example:「実際に利用者の80%が効果を実感しています」
- Point:「だから今すぐ体験してください」
- 営業資料
- Point:「このツールで業務効率が改善します」
- Reason:「理由は作業時間を自動化で大幅に削減できるからです」
- Example:「A社では導入後に作業時間が半分になりました」
- Point:「だから御社でも導入する価値があります」
AIを使ったPREP法の学習方法
生成AIはPREP法の練習に最適です。
- 「このテーマをPREP法で書いて」
- 「結論を強調して」「理由を3つに増やして」
- 「Exampleを数字データ付きに書き換えて」
と指示を変えることで、同じテーマを様々なバリエーションで練習可能です。
さらに、自分で書いた文章をAIに渡して、
- 「この文章をPREP法に整理して」
- 「結論が弱いので強めて」
と添削させれば、即時フィードバックを得られます。
まとめ:PREP法は副業ライターの即戦力スキル
PREP法をマスターすれば、短時間で論理的かつ説得力のある文章が書けるようになります。特に副業ライターが狙うLP・広告・提案資料といった案件では「PREP法だけで8割対応できる」と言っても過言ではありません。
SDS法(要点 → 詳細 → 要約)
SDS法は、短時間で読者に情報を理解させたいときに効果的な構成です。
最初に要点を伝え、次に詳細を展開し、最後に再度まとめる――ニュース記事やプレゼン資料など、限られた時間で相手に内容を落とし込みたい場面に最適です。
SDS法の基本構造とポイント
- Summary(要点)
- 最初に「何について書くのか」を簡潔に伝える。
- 読者は冒頭で「この文章が自分に必要か」を判断できる。
- コツ:一文でズバッとまとめる。
- Details(詳細)
- 要点を支える情報や説明を展開するパート。
- 複数の理由や背景を整理して書くと説得力が増す。
- コツ:箇条書きや段落分けを活用し、読みやすさを意識。
- Summary(要約)
- 最後にもう一度、冒頭で述べた要点を簡潔にまとめる。
- 読者が読み終わった後に「理解できた」と感じられる。
- コツ:シンプルに繰り返すことで記憶に定着する。
副業案件での活用例
- SEO記事
検索ユーザーは「答えをすぐに知りたい」と思っている。SDS法を使えば、冒頭で結論を示し、その後に詳細を展開、最後にまとめで整理することで、離脱率を下げられる。 - 教材・研修資料
講義や研修では「分かりやすさ」が最優先。SDS法で要点を先に伝えると、学習者は内容を理解しやすい。 - プレゼン資料
上司やクライアントへの報告は「結局どういう話?」を冒頭で伝える必要がある。SDS法は短時間のプレゼンに特に効果的。
AIを使ったSDS法の学習方法
生成AIを活用すれば、SDS法の習得が効率化します。
- 「この内容をSDS法で整理して」
- 「要点を冒頭で一文にまとめて」
- 「まとめ部分を読者が行動したくなる形に書き換えて」
さらに、同じテーマをPREP法とSDS法で書かせて比較すると、「説得型」と「理解型」の違いを体感できます。
まとめ:SDS法は「理解を優先した文章」に最適
SDS法を使うと、読者は冒頭で方向性を理解し、詳細で納得し、最後に再確認できます。つまり「迷子にさせない文章」が書けるのです。
副業ライターにとって、SEO記事や教材案件では必須の構成法といえるでしょう。
ストーリー構成(起承転結・物語)
人は論理だけで動くのではなく、感情によって行動を決断する生き物です。そこで威力を発揮するのが「ストーリー構成」。単なる説明文ではなく、物語として展開することで、読者は自然と引き込まれ、共感や信頼を抱きやすくなります。
ストーリー構成の基本パターン
- 起(導入)
- 主人公(読者や顧客に重ね合わせられる人物)の状況や課題を提示。
- 「これは自分の話かもしれない」と共感してもらうことが重要。
- 承(問題の深掘り)
- 課題がなぜ大きな悩みになるのかを描写。
- 感情を揺さぶり、課題解決の必要性を強調する。
- 転(解決の糸口)
- 解決策や商品・サービスの登場。
- 「この方法なら自分も変われる」と希望を持たせる。
- 結(解決・未来)
- 課題を解決した未来像を提示。
- 読者に「自分もこうなれる」とイメージさせる。
副業案件での活用例
- SNS投稿
短いストーリーを展開することで「共感 → シェア」の流れを作れる。 - セールスコピー
商品を“物語の主人公の救い”として登場させると、自然な訴求になる。 - 動画台本
視聴者はストーリーで引き込まれる。起承転結の流れはYouTubeやTikTok台本に最適。
AIを使ったストーリー構成の学習方法
生成AIは、ストーリー展開の練習にも役立ちます。
- 「このテーマを起承転結で説明して」
- 「ペルソナを主人公にしてストーリーを作って」
- 「問題を強調したドラマチックな導入に書き直して」
と依頼すれば、複数のストーリーパターンを瞬時に生成できます。これを比較し、人間が“感情の動きを意識して”取捨選択することで、説得力と共感力を両立した文章力が鍛えられます。
まとめ:ストーリーは「感情を動かす武器」
PREPやSDSが「論理で伝える型」なら、ストーリー構成は「感情を動かす型」です。副業ライターにとって、SNSや広告、動画シナリオなど幅広い案件で使える強力な武器となります。
AI比較学習の活用
文章構成を学ぶときにありがちな問題は、「頭では理解したけど、実際にどう違うのかイメージしにくい」という点です。ここで力を発揮するのが生成AIを使った比較学習です。
AI比較学習のやり方
- 同じテーマを複数の型で書かせる
- 「このテーマをPREP法で」
- 「同じテーマをSDS法で」
- 「ストーリー形式で展開して」
- 文章を自分で書いてAIに整理させる
- 「この文章をPREP法に整理し直して」
- 「要点をSDS法に要約して」
- 改善指示を出してブラッシュアップ
- 「このPREP法の結論をもっと強めて」
- 「SDS法の要約をよりシンプルにして」
- 「ストーリーを感情に訴える形に書き直して」
副業ライターが得られるメリット
- 習得スピードが圧倒的に早い:一度に複数の型を比較できるから、違いを体感で理解できる
- 案件対応力が広がる:LPはPREP、SEO記事はSDS、SNSや動画台本はストーリー…と媒体に応じて使い分け可能
- フィードバックを自走できる:AIが常に添削してくれるので、独学でも成長できる
まとめ:AIで「型を体感的に学ぶ」
構成力は本を読んで理論を学ぶだけでは身につきません。実際に書いて、比べて、修正することで初めて自分のスキルになります。
生成AIを活用すれば、このサイクルを短時間で何度も回せるため、副業ライターでも効率よく「伝わる文章の型」を習得できるのです。
まとめ:型を使い分けることで文章は一気に伝わる
Webライティングの現場では、ただ文章を書くだけでなく、状況に応じて最適な構成を選べる力が求められます。
- PREP法 → 論理的に説得したいとき(LP・営業資料・広告コピー)
- SDS法 → 短時間で理解してほしいとき(SEO記事・教材・プレゼン資料)
- ストーリー構成 → 感情を動かしたいとき(SNS・セールスコピー・動画台本)
これら3つを自在に使い分けられれば、副業ライターとして幅広い案件に対応できます。
さらに生成AIを使えば、同じテーマを複数の型で出力して比較できるため、構成の違いを体感で理解しながら習得スピードを加速できます。
つまり、文章構成の基礎をAIとともに学ぶことは、「読者に伝わる文章」への最短ルートなのです。
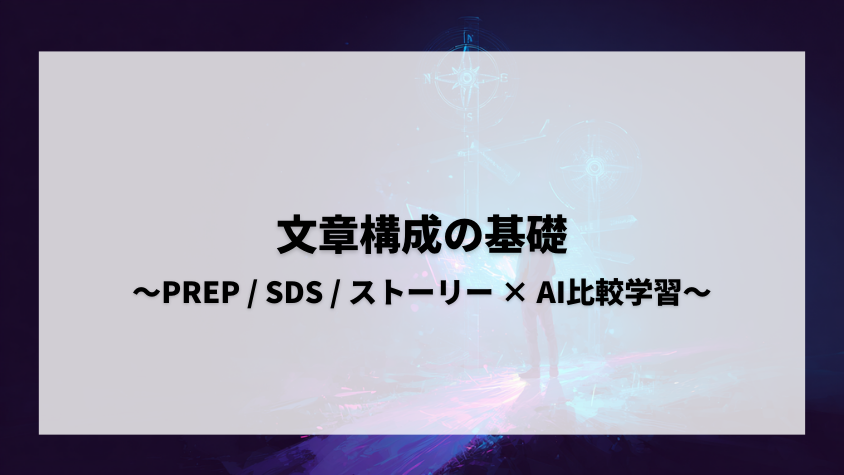
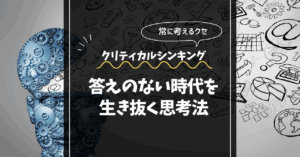
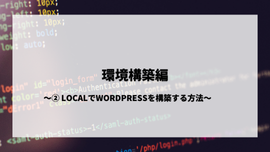
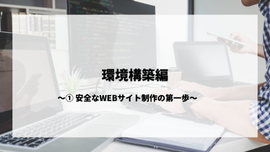

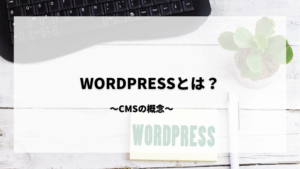
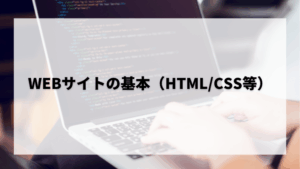
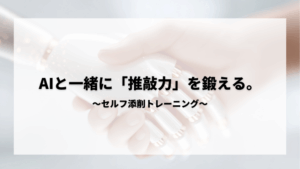
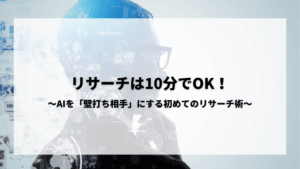
コメント